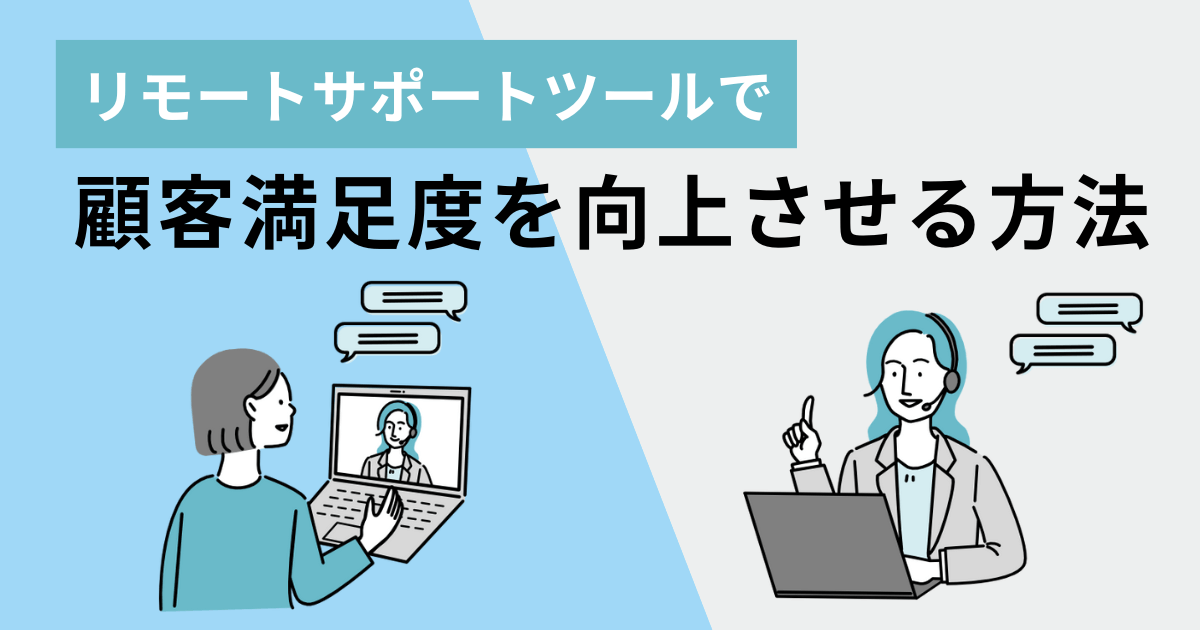リモートサポートとは?顧客満足度と業務効率を上げる導入ガイド
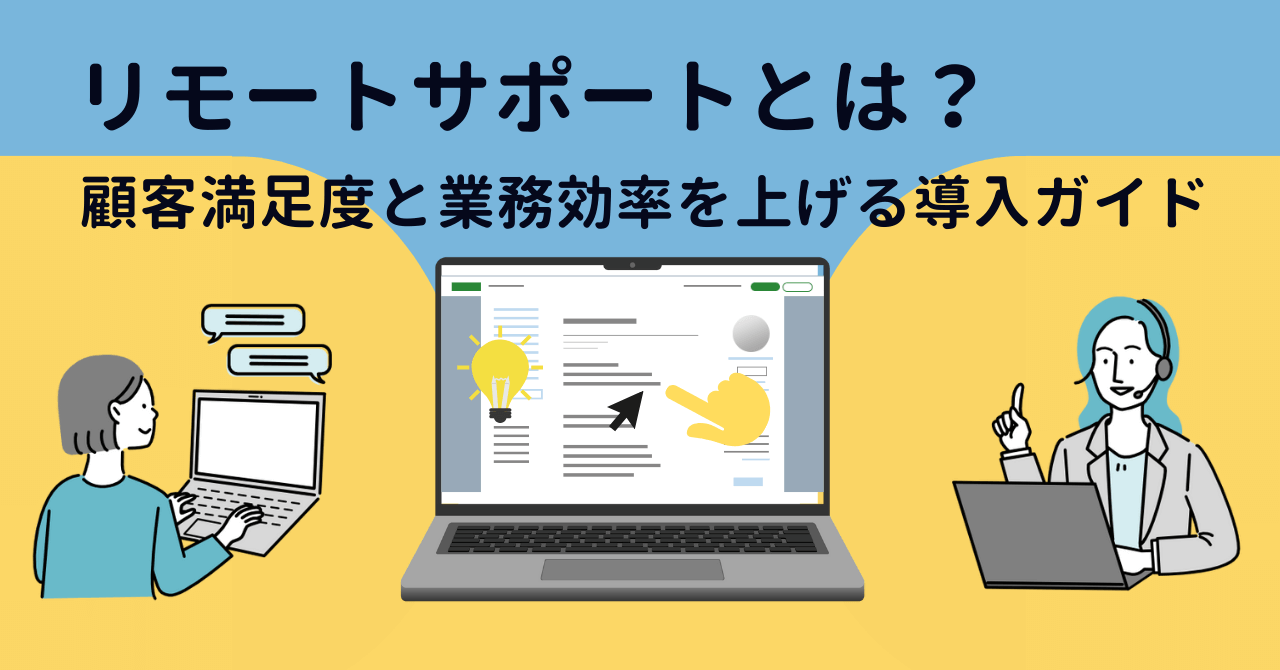
顧客対応の現場では、応対スピードと満足度の両立が大きなテーマとなっています。とくにコンタクトセンターやテクニカルサポートの現場では、限られた人員と時間の中で、いかに“的確に・迅速に・丁寧に”問題を解決できるかが成果を左右します。
そんな中で注目されているのが、「リモートサポート」という手法です。従来の電話やメールに加え、画面共有・共同操作・ビデオ通話など可能なツールを活用することで、まるで目の前で接客しているかのような体験を顧客に届けることが可能になります。
もくじ
リモートサポートとは?
リモートサポートとは、オペレーターが顧客と物理的に離れた場所にいながら、リアルタイムで問題の解決や操作支援を行うサポート手法です。従来の電話やメールでは伝えにくかった技術的なトラブルや操作案内も、視覚的・操作的なアプローチを組み合わせることで、よりスムーズかつ正確にサポートを提供できるのが大きな特長です。
近年では、さまざまな機能を統合したリモートサポートツールが登場し、以下のような機能を組み合わせて活用するのが一般的になっています。
たとえば、ビデオ通話を使って「顔が見える」安心感のあるコミュニケーションを実現し、画面共有や資料共有によって複雑な操作も可視化しながら説明できます。また、チャット機能によって口頭で伝えにくい細かな指示やURL、画像ファイルなどの共有も簡単に行えます。
さらに、Webページを顧客と同時に操作する「コブラウズ」機能では、オペレーターが実際の画面上でナビゲーションしたり、必要に応じて遠隔操作による直接的な支援も可能です。応対のすべての履歴は記録・保存され、後からの参照やトラブル対応、品質管理にも役立ちます。
このようにリモートサポートは、従来の「訪問しなければ対応できない」「電話だけでは伝わらない」といった制限を取り払い、非対面でも高品質なサポート体験を可能にする新しい支援のスタンダードとして、幅広い業種で導入が進んでいます。
リモートサポートの主な機能とできること
リモートサポートが注目を集める背景には、単に「遠隔で接続できる」だけでなく、顧客体験の質を高め、サポート業務の生産性を向上させる多彩な機能群の存在があります。ここでは、現場で実際に活用されている主要機能と、それによって実現できることをご紹介します。
ビデオ通話・チャットで“顔の見える”サポート
従来の電話対応だけでは、声のトーンや言葉のニュアンスから相手の状況を完全に把握するのは難しい場面もありました。しかし、ビデオ通話を活用すれば、オペレーターと顧客が顔を合わせながら会話できるため、より安心感のある対話が可能になります。
さらに、チャット機能を併用することで、口頭では伝えにくい長いURLや操作手順、画像などもリアルタイムで共有でき、視覚的な補足が加わることでスムーズな対応が実現します。
画面共有・資料共有で状況把握がスムーズ
特にテクニカルサポートや業務支援では、「見ればすぐにわかること」が、口頭での説明だけでは伝わらず、時間がかかってしまうケースも少なくありません。画面共有機能を使えば、顧客の画面を一緒に見ながら状況を把握し、具体的な指示を出すことができます。
たとえば、「申込みフォームのどこに入力していいかわからない」「このボタンを押した後どうすれば?」といった操作の迷いを即時に解消でき、サポートの品質とスピードを両立することが可能です。また、PDFや画像、マニュアルなどの資料もその場で共有できるため、説明と補足の一体化にも効果的です。
コブラウズ(共同操作)で“代わりに操作”
より高いサポート体験を提供するためには、「案内するだけ」でなく、「一緒に操作する」ことも重要です。コブラウズ機能を使えば、オペレーターが顧客と同じWeb画面を見ながら、必要に応じて一部の操作を代行したり、入力を支援したりすることが可能になります。
電話やチャットで「〇〇のページを開いて、下の方にあるボタンを押してください」と説明しても、うまく伝わらないケースはよくあることですが、コブラウズを使えば、オペレーターが顧客の画面上に「ここをクリックしてください」とポインタを表示したり、必要に応じてフォーム入力を代行することが可能です。オンライン申請フォームの記入補助や、契約手続き時の確認作業など、ミスが許されない重要な局面でも的確にサポートできます。結果として、誤入力や途中離脱の防止、そして顧客満足度の向上につながります。
応対履歴・ログ保存で品質の一元管理
どんなに丁寧なサポートを行っていても、「言った・言わない」のトラブルや、後からの振り返りが必要になる場面は存在します。リモートサポートツールには、応対ログやチャット履歴、画面共有の記録、録音・録画などを自動で保存する機能が備わっているものも多く、トラブル防止や品質管理の観点でも有効です。
また、過去のやり取りをスタッフ同士で共有することで、対応の属人化を防ぎ、ナレッジとして蓄積することが可能です。新人研修やCS向上プロジェクトにも活用でき、サポート体制全体の底上げにつながります。
サポート現場で今、なぜリモートサポートが求められるのか
リモートサポートが急速に注目を集めている背景には、顧客対応の質とスピード、そして現場の生産性向上という3つのニーズが同時に高まっている現状があります。ここでは、現場の視点からリモートサポートが求められる理由を3つの軸で解説します。
顧客対応スピードと品質の両立
これまでの電話対応やメールサポートでは、「うまく伝わらない」「時間がかかる」といった課題がつきものでした。特に操作が絡む問い合わせや複雑なトラブルにおいては、言葉だけでは限界があり、何度もやりとりを繰り返すうちに、顧客の不満やストレスが増してしまうこともあります。
リモートサポートでは、ビデオ通話・画面共有・コブラウズなどの機能を活用することで、“見せながら・一緒に操作しながら”対応できるため、一次対応での解決率を飛躍的に高めることができます。オペレーターと顧客がその場で状況を共有し、リアルタイムに解決へ導くことで、サポート体験そのものの質が向上します。
拠点やチャネル多数化への対応力向上
近年、サポート業務は1つの拠点だけで完結するものではなくなりました。全国に拠点を展開する企業や、在宅勤務を導入しているコンタクトセンターにとって、「どこにいても、誰でも同じ品質で対応できる仕組み」が求められています。
リモートサポートは、ネットワークにつながる環境さえあれば、場所を問わず均質な顧客対応が可能です。拠点間での情報共有や対応履歴の一元化がしやすく、在宅オペレーターでも高品質なサポートを提供できます。これにより、柔軟な人員配置やサポートの分散処理も可能になり、対応体制の強化につながります。
業務効率化とスタッフ負担軽減
訪問サポートや、複数回の電話・メールでのやり取りは、スタッフにとっても大きな負担です。リモートサポートの導入により、1件あたりの対応時間を大幅に短縮することができ、人的リソースの効率的な運用が可能になります。
また「わからない」「伝わらない」といったフリクションが減ることで、オペレーターの精神的な負荷も軽減されます。これにより、業務の生産性を向上させながら、スタッフの離職率低下や職場満足度の向上といった副次的効果も期待できます。
導入フェーズで陥りがちな落とし穴とその回避方法
リモートサポートツールを導入する際、単に「便利そうだから導入する」という姿勢では、現場でうまく活用されず、効果が出ないまま終わってしまうことも少なくありません。特にコンタクトセンターやカスタマーサポート現場では、オペレーションの一部に新しい手法を加える以上、組織的な整備や現場との連携が不可欠です。
ここでは、導入時に企業がつまずきやすいポイントと、それを回避するための具体的な方法を解説します。
意思決定者と現場ギャップの解消
導入の失敗要因としてよくあるのが、意思決定者と実際に現場でツールを使用するオペレーターとの間で、期待値や理解にズレが生じているケースです。たとえば、経営層や情報システム部門が「コスト削減になる」「顧客満足度が上がるはず」と考えて導入を進めたものの、現場では「操作が難しい」「既存フローと合わない」といった不満が噴出する、といった状況です。
これを防ぐには、初期段階から現場の意見をヒアリングし、課題感や不安を洗い出しておくことが大切です。ツール選定の段階から、実際のユーザーを巻き込み、「現場で本当に使える仕様」になっているかを確認しましょう。導入後に「現場に受け入れられない」事態を防ぐためにも、経営と現場の認識のすり合わせが欠かせません。
研修・マニュアル整備が導入後の定着を左右する
どんなに優れたツールでも、使う人が戸惑っていては意味がありません。導入初期には、操作方法をしっかり習得してもらうための研修が必須です。また、業務フローの中で「どこで、どう使うか」が明確になっていないと、結局使われずに形骸化してしまいます。
そのためには、以下のようなサポート体制を整えておくことが重要です。
- スタッフ向けの操作研修(オンライン・オフラインどちらでも)
- 業務フローに沿ったマニュアル整備(PDFや社内Wikiなど)
- よくある質問(FAQ)の事前共有
- 社内におけるサポートデスクの設置
また、動画マニュアルやステップガイドのような視覚的な資料も有効です。とくに非テクニカルなスタッフが多い場合は、「使ってみてわかる」UIサポートと「困ったときに戻れる」マニュアルの両輪が、定着の鍵を握ります。
KPI設定と効果測定の定着化
導入の目的が曖昧なままでは、効果が見えづらく、改善も進みません。だからこそ、「何のために導入するのか」「何をもって成功とするのか」を、KPIとして明確に設定することが重要です。
代表的なKPI例:
- 一次対応での解決率(ファーストコンタクトレゾリューション)
- 1件あたりの応対時間
- 顧客満足度(CSAT・NPS)
- 再入電率(リピートコール率)
- スタッフのツール使用率
導入前と後での比較によって「リモートサポートによって何が変わったか」が可視化され、現場のモチベーションにもつながります。定量的な評価指標と、現場からの定性的フィードバックを両軸で捉えながら、PDCAを回していくことが、持続的な活用に向けた第一歩となります。
業種別の活用シーンと成果
リモートサポートの導入は、特定の業種に限定されるものではなく、多様な業界で成果を生んでいます。ここでは、業種ごとの活用シーンと導入による具体的な効果をご紹介します。
通信・インフラ企業
通信回線やネットワーク機器に関するサポートでは、「接続できない」「Wi-Fiの設定がわからない」といったテクニカルな問い合わせが日常的に発生します。こうした問題に対して、リモートサポートでは画面共有やコブラウズを活用しながら、オペレーターがリアルタイムで状況を把握し、手順を示したり操作を補助することが可能です。
訪問対応が不要となるため、応対スピードが大幅に向上し、1件あたりの解決時間の短縮にもつながります。また、設定ミスや操作ミスを即時に発見できることで、トラブルの再発防止にも貢献します。
金融・保険業界
金融・保険業界では、Web口座開設や保険申請など、オンラインでの手続きが増える一方で、「途中で離脱されてしまう」「入力内容に不備がある」などの課題が多く見られます。
リモートサポートを導入することで、オペレーターが顧客と同じ画面を見ながら操作をサポートできるため、複雑なフォーム記入や書類アップロードもスムーズに進行します。さらに、ビデオ通話機能による本人確認も可能となり、非対面でありながら厳格な手続きを担保できます。
結果として、離脱率の低下、顧客満足度の向上、そして業務効率化を同時に実現できます。
SaaS・IT企業
SaaSやITサービスを提供する企業にとって、顧客がサービスを使いこなせないことによる解約は大きな課題です。リモートサポートを活用すれば、ログイン設定や初期のアカウント設定などでつまずくユーザーに対して、画面共有やチャットで直接支援することができます。
たとえば、「どこから設定画面に入るのかわからない」「APIキーの場所が見つからない」といった初期段階での問い合わせにも、視覚的な支援を通じて迅速に対応。導入から定着までのプロセスをしっかりサポートすることで、顧客の満足度と継続利用率の向上に貢献します。
製造業・家電サポート
製造業や家電製品のアフターサポートでは、「現場に行かないとわからない」という理由で出張対応が必要になることが少なくありません。しかし、リモートサポートを活用すれば、顧客側のスマホカメラで現場の映像を映してもらいながら、状況を確認・指示することができます。
「本当に故障なのか」「操作ミスではないか」といった一次判断をその場で行えるため、訪問の必要がなくなるケースも多く、コスト削減と対応スピードの両立が実現します。加えて、サポート品質の均一化や、現場負担の軽減にもつながります。
リモートサポート導入時のツール選定ポイント
リモートサポートツールの導入にあたっては、単に「遠隔接続できる」だけでは不十分です。顧客体験の質や業務運用の効率、安全性を最大化するためには、導入前に以下の観点からツールを比較・検討することが重要です。
セキュリティとプライバシー保護の信頼性
顧客の個人情報や業務機密を扱うサポート業務では、セキュリティ対策が最優先事項です。SSLによる通信の暗号化や、ログの保存・管理、操作履歴の記録といった機能が備わっているかを確認しましょう。また、オペレーターのアクセス権限を細かく設定できるアクセスコントロール機能も、情報漏洩リスクを防ぐうえで不可欠です。
ノンアプリ・ワンクリックで接続できるか
顧客が特別なアプリをインストールする必要があるツールは、操作に不慣れなユーザーや高齢の利用者にとってハードルとなります。その点、ブラウザだけでワンクリック接続が可能なノンアプリ型のリモートサポートツールは、誰でも迷わず接続でき、サポート開始までの時間を最小限に抑えることができます。UI/UXのわかりやすさもツール選びの重要な判断材料です。
コブラウズ・画面操作補助の有無
顧客のWeb画面上で「どこを操作すればいいか」を一緒に確認しながらサポートできるコブラウズ機能や、フォーム入力などの操作をオペレーター側から支援できる機能は、顧客の負担軽減に直結します。特に手続きが複雑な業種(金融、不動産、IT系SaaSなど)では、操作ミスや途中離脱を防ぎ、完了率の向上にも大きく貢献します。
応対ログの記録・分析機能が整っているか
業務の改善やトラブル発生時の対応、社内教育などを目的とする場合には、ログ管理や分析機能があるかどうかも重要なポイントです。チャット履歴、通話録音・録画、画面共有の内容といったやり取りを記録できることで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、監査対応や品質管理の面でも大きな安心材料となります。さらに、蓄積した応対ログを分析することで、ボトルネックの把握やFAQ整備などにも役立てることができます。
LiveCallで実現する安心・高品質なリモートサポート
これらの観点から、企業におすすめしたいリモートサポートツールがLiveCall(ライブコール)です。LiveCallは、非対面での顧客支援を可能にする国産のクラウド型ビデオ通話プラットフォームで、サポートの現場に最適化された機能を多数搭載し、大手企業から中小企業まで、数多くの企業に導入いただいています。

LiveCallの主な特長
- ノンアプリ・ワンクリック接続
顧客側のアプリインストール不要。URLをクリックするだけで接続できるため、ITリテラシーを問わず導入可能です。 - 画面共有・コブラウズ(共同操作)
オペレーターが顧客と同じWebページを一緒に見ながら操作補助ができるため、入力ミスや途中離脱を防ぎます。 - ビデオ通話・チャット機能
顔が見える対応で安心感を提供しつつ、チャットでの資料送付や補足説明も可能です。 - エンベット通話・チャット
サイト上に埋め込めるウィジェットを通じてチャットやビデオ通話による対応も可能です。お客様は閲覧しているページを離れることなくサポートを受けられます。 - 応対ログの記録・保存
ビデオ通話の録画やチャットログの保存ができ、トラブル対応や内部監査、業務改善に役立ちます。 - セキュリティ対応
金融機関や医療機関でも利用されている高いセキュリティ設計。SSL通信、ログ管理、アクセス制限などの要件も網羅しています。 - 豊富な業種別導入実績
コンタクトセンター・カスタマーサポート部門だけでなく、医療・行政・不動産・金融業界など多様な分野で導入実績があり、活用ノウハウも豊富です。
LiveCallを活用することで、サポート業務の品質と効率を飛躍的に高めることが可能になります。
まとめ:顧客体験と業務効率を両立する「リモートサポート」の可能性
リモートサポートは、顧客満足度と業務効率を両立したいと考える企業にとって、もはや「選択肢の一つ」ではなく「新しい標準インフラ」として注目されています。特にコンタクトセンターやカスタマーサポート、テクニカルサポートの現場においては、従来の電話やメールだけでは実現が難しかった“リアルタイムでの視覚的な支援”を可能にし、応対の質を飛躍的に向上させる手段として定着しつつあります。
画面を共有し、フォーム入力を支援し、必要に応じて共同で操作を行う。そんなサポート体験は、顧客の不安や手間を大幅に軽減し、ブランドへの信頼とロイヤリティを高める重要な接点となります。さらに、応対履歴の保存やナレッジ共有を通じて、組織全体の対応品質を継続的に改善できる点も、企業にとって大きな強みです。
今後の顧客対応では、「効率」だけでなく「体験価値」も提供できる体制が求められます。そのためには、技術面・運用面・顧客体験の3つの視点から、自社に最適なリモートサポートツールと運用体制を整えることが不可欠です。
LiveCallは、そうしたニーズに応えるべく、ビデオ通話・画面共有・コブラウズ・通話履歴管理・エンベッド通話といった多彩な機能を備え、あらゆる業種・業務にフィットする柔軟な設計が可能です。サポート現場のリアルを熟知したチームが、導入前の課題整理から定着支援までしっかり伴走いたします。
導入をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。自社の体制や課題に合わせた最適な運用方法をご提案します。
\合わせて読みたい「リモートサポート」関連記事/
無料トライアルも実施中!
LiveCallは、アプリ不要・サイトにリンクを貼るだけで、簡単にオンライン接客をスタートできます。
活用方法なども担当営業よりご提案いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
関連記事一覧