カスタマーサポートツールの選び方|比較・導入メリット・最新機能を紹介
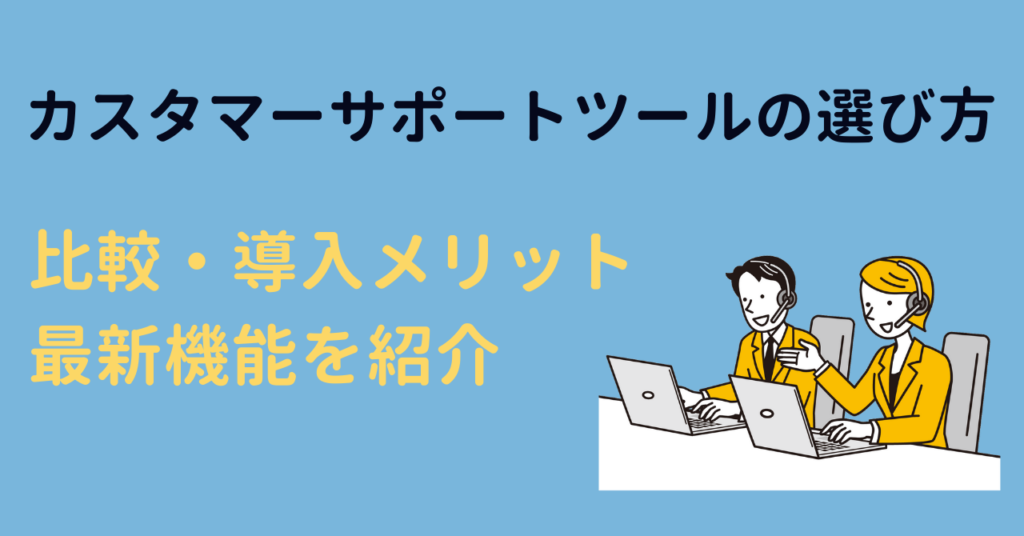
企業にとって「顧客対応」は、商品やサービスそのものと同じくらい重要な価値を持っています。顧客が問い合わせをした際にスムーズで安心感のある対応ができれば、顧客満足度が高まり、リピート購入や口コミにつながります。逆に、問い合わせ窓口での対応に時間がかかったり、解決できなかったりすると、不満がSNSなどに拡散され、ブランドイメージの低下を招くリスクもあります。そのため、近年ますます注目を集めているのが「カスタマーサポートツール」です。
かつてカスタマーサポートといえば、電話やメールでの対応が一般的でした。しかし2025年の今、企業はこれだけでは顧客の期待に応えきれなくなっています。顧客が求めているのは「早く」「的確で」「負担の少ない」対応です。そこで注目されているのが、複数のチャネルを統合して効率的に運用できるカスタマーサポートツールです。
特に注目されているのが、Webサイトやアプリに埋め込み、顧客と直接チャットやビデオ通話ができるツールです。従来のメールや電話では「状況を正しく把握できない」「言葉で説明しにくい」という課題が多く見られました。たとえば「商品が届いたが部品の使い方がわからない」といったケースでは、メールで写真を送ってもらい、文章で説明するしか方法がなく、顧客側もサポート側も大きな負担になっていました。
そこで「ビデオ通話型カスタマーサポートツール」を導入すると、顧客がカメラ越しに現物を見せながら相談でき、担当者もその場で的確な案内を行うことが可能になります。さらに画面共有やコブラウズ機能を使えば、「オンライン手続きがうまくできない」「アプリの操作方法がわからない」といった問題も一緒に画面を見ながら解決できます。これは従来のサポートチャネルにはない大きなメリットで、多くのカスタマーセンターやコンタクトセンターに導入されています。
近年は、スタートアップから大手企業まで幅広い業種でカスタマーサポートツールが導入され、競争力の源泉になりつつあります。特にチャット型、ビデオ通話型ツールを組み込むことで、オンライン上でも店舗での接客に近い顧客体験を提供できるようになりました。これにより、顧客は「顔が見える安心感」を得られ、企業は顧客対応にかかる時間や工数を削減しながら満足度を高められます。
もくじ
カスタマーサポートツールとは?
カスタマーサポートツールとは、顧客からの問い合わせや相談に対して効率的かつ高品質な対応を行うためのITシステムの総称です。従来は「電話やメールを受け付ける窓口」だけが主流でした。しかし今では、チャットやSNSでの対応、FAQサイトやチャットボットによる自己解決支援、そしてビデオ通話を活用したリアルタイム接客など、チャネルは多様化しています。企業はこうした複数チャネルを効率的に管理し、顧客にシームレスな体験を提供する必要があります。
カスタマーサポートツールの役割は単に「対応を効率化すること」だけではありません。企業にとっての本質的な価値は、顧客体験(CX)の質を高め、ブランドロイヤリティを育てることにあります。スムーズでストレスのないサポートを提供できるかどうかは、顧客が「この会社の商品やサービスをこれからも使いたい」と思うかどうかを左右します。つまり、カスタマーサポートツールは顧客満足と業務効率の両立を支える存在です。
なぜ今、カスタマーサポートツールが必要なのか
なぜ今これほどまでにツールが重要視されているのでしょうか。その背景には、いくつかの大きな変化があります。
非対面チャネルの拡大
まず、非対面での顧客接点が急速に広がっていることが挙げられます。顧客はもはや電話だけでなく、チャット、LINE、メール、さらにはビデオ通話など、自分の都合の良い方法で企業とつながりたいと考えています。特に若い世代は「電話よりチャット」の傾向が強く、また高齢者層でも「画面を見ながら説明を受けられるビデオ通話」に安心感を感じるケースが増えています。
このように、顧客の期待に応えるためには複数チャネルを提供することが必須です。しかし、すべてを個別に運用していては管理が煩雑になり、かえって対応品質が落ちてしまいます。ここで役立つのがカスタマーサポートツールです。ツールを導入すれば、複数のチャネルを一元管理でき、効率的にサポートを提供できます。
人手不足・業務負荷の増加
次に、深刻化する人手不足と業務負荷の問題があります。限られたスタッフで膨大な問い合わせに対応しなければならない状況では、従来の体制だけでは限界があります。特にECや金融など、サポート需要が高い業界では、問い合わせ対応が追いつかず「対応待ち」「回答遅延」といったトラブルが発生しがちです。
カスタマーサポートツールには、問い合わせの自動振り分けやFAQによる自己解決支援、チャットボットによる一次対応といった機能が備わっています。これにより、単純な問い合わせは自動化し、複雑で重要なケースだけを人間の担当者が対応できるようになります。その結果、スタッフの負担を軽減しつつ、顧客満足度を維持することが可能になるのです。
顧客体験(CX)重視のトレンド
さらに、近年のビジネスでは「CX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)」が競争力の源泉とされています。どれだけ商品やサービスが優れていても、サポート対応に不満を感じれば顧客は離れてしまいます。逆に、迅速で誠実な対応を受けた顧客は「この会社なら信頼できる」と感じ、長期的な関係を築いてくれるのです。
特にLiveCallのように「顔を見ながら会話できるツール」を導入すると、非対面でありながら対面に近い安心感を提供できます。これはCXを高め、競合との差別化につながる大きなポイントです。
働き方の多様化への対応
最後に、働き方の多様化があります。リモートワークや在宅勤務が広がった今、従来の「オフィスに集まって電話を取る」スタイルでは十分な対応ができません。カスタマーサポートツールをクラウドで導入すれば、スタッフは場所を問わず顧客対応が可能になります。これにより、柔軟な働き方を実現しつつ、顧客へのサービス品質も保つことができます。
こうした背景から、カスタマーサポートツールは「単なる便利なツール」ではなく、現代のビジネスにおける必須インフラと言える存在になりました。非対面チャネルの拡大、人手不足の解消、CX向上、働き方改革——これらすべての課題に応えるために、ツールの導入は避けて通れない選択肢です。
特に、ビデオ通話や画面共有機能を持つLiveCallのようなツールは、「顧客の困りごとをその場で一緒に解決できる」点で従来の仕組みを超える価値を提供します。今後さらに多くの企業が導入を検討する理由も、ここにあるのです。
カスタマーサポートツールの主な機能
カスタマーサポートツールには多様な機能があります。これらは単に業務を効率化するだけでなく、顧客体験の質を大きく左右する重要な要素です。ここでは、代表的な機能とその役割を整理してみましょう。
1. 問い合わせ管理(チケット制・自動仕分け)
最も基本的な機能は、顧客からの問い合わせを一元管理する仕組みです。電話やメール、チャットなど複数チャネルから入る問い合わせを「チケット」として登録し、担当者に自動で割り当てたり、緊急度や内容に応じて振り分けたりできます。
従来のように「誰がどの問い合わせを対応しているのかわからない」という状況を防ぎ、対応漏れや二重対応を解消します。顧客にとっても「回答が遅い」「たらい回しになる」といった不満を減らせるため、満足度向上につながります。
2. 顧客情報の一元管理
次に重要なのが、顧客情報を集約して一元的に管理できる機能です。名前や連絡先といった基本情報だけでなく、過去の問い合わせ履歴や購入履歴、サポートの対応内容などをまとめて確認できます。
これにより「前回と同じ内容をまた説明しなければならない」という顧客のストレスを解消できます。担当者も顧客の背景を理解したうえで対応できるため、よりパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。
3. FAQ・チャットボット・AI対応
近年急速に普及しているのが、顧客自身で問題を解決できる自己解決支援機能です。FAQページやチャットボットを整備すれば、簡単な質問や手続きは顧客が自ら解決できます。
また、AIによる自然言語処理を活用すれば、顧客が入力した文章を理解し、最適な回答や関連ページを提示できます。これにより、サポート担当者は複雑で高度な問い合わせに集中できるようになり、業務効率と顧客満足度の両立が実現します。
4. 有人チャット(ライブチャット)
自己解決が難しい場合には、人がリアルタイムで対応する有人チャットが効果を発揮します。チャットボットの限界を超える複雑な相談やニュアンスの理解が必要なケースでは、担当者が即座に引き継ぐことでスムーズな対応が可能です。
有人チャットは電話よりも手軽に利用できるため、特に若い世代の顧客に好まれる傾向があります。さらに、顧客がWebサイト上で操作をしながらその場で質問できるため、離脱防止や購入支援にも直結します。
5. ビデオ通話・画面共有・コブラウズ
ここ数年で急速に注目されているのが、リアルタイムで顧客と同じ画面を見ながらサポートできる機能です。特にLiveCallのようなツールは、Webサイトに埋め込むだけでビデオ通話や画面共有・画面同期(コブラウズ)を簡単に実現できます。
例えば「オンライン申込フォームの入力がうまくいかない」「アプリの操作がわからない」といった場合、電話やメールでは解決に時間がかかります。しかし、ビデオ通話なら顧客の画面をそのまま見ながら一緒に操作できるため、短時間で確実な解決が可能です。
また、製品の組み立てや修理サポートでも「現物をカメラ越しに見せてもらい、その場で説明する」ことができ、対面に近い顧客体験を提供できます。これは、従来のサポートツールにはなかった強力な付加価値です。
6. 対応履歴の記録・分析・レポート
最後に欠かせないのが、対応履歴を蓄積し、分析・レポートを行う機能です。誰がどのように対応したかを記録することで、品質管理や教育に活かせます。さらに、問い合わせ件数の推移や顧客の傾向を分析すれば、製品改善やサービス強化のヒントが得られます。
例えば「特定の商品について同じ質問が多い」ことが分かれば、FAQやマニュアルを改善することで、問い合わせ件数自体を減らすことも可能です。
カスタマーサポートツールの機能は、単に業務を支援するだけでなく、顧客の利便性と満足度を高める仕組みそのものです。中でもLiveCallのように、ビデオ通話や有人チャット、画面同期によって「その場で問題を一緒に解決できる機能」を備えたツールは、CX向上に直結する大きな強みとなります。
有人チャット・ビデオ通話を導入するとどう変わる?(ビフォー・アフター)
カスタマーサポートツールの導入効果を実感していただくために、ここでは有人チャットとビデオ通話を導入した場合の変化 を「ビフォー・アフター」の形で整理してみましょう。
導入前の課題
多くの企業が直面している顧客対応の課題は、次のようなものです。
電話やメールでは状況把握が困難
顧客から「エラー画面が出る」「部品がうまくはまらない」といった問い合わせがあっても、言葉だけでは正確に状況を理解するのは難しいものです。そのため、何度もやり取りを繰り返し、解決に時間がかかってしまいます。
顧客のストレスが大きい
顧客にとっても「何度も説明しなければならない」ことは大きな負担です。とくにデジタル操作に不慣れな顧客は、説明の途中で諦めてしまうケースもあります。
サポート担当者の負荷が高い
メールでの長文対応や電話での繰り返し説明は、担当者の精神的・時間的コストを増大させます。結果として、対応件数の増加に追いつけず、全体の対応品質も低下してしまいます。
有人チャットとビデオ通話導入後の変化
これらの課題に対して、有人チャットとビデオ通話はどのような変化をもたらすのでしょうか。
有人チャットで問い合せ内容を把握
ファーストステップとして有人チャットで対応することで、顧客が「今まさに困っている」内容を把握することができます。FAQやAIによる自動返信だけでは把握しきれない部分も、顧客の目線にたって人が対応することで詳細がわかります。
ビデオ通話で状況を即座に把握
顧客がカメラを通じて「今まさに困っている状況」を見せることで、担当者は一目で問題を理解できます。これにより、解決までに必要なやり取りが大幅に削減され、対応スピードは従来比で30〜40%改善するケースもあります。
画面共有・コブラウズで操作を一緒に実施
「アプリの操作ができない」「申込フォームがうまく送信できない」といったケースでは、担当者が顧客と同じ画面を共有しながら案内できます。そのため、顧客は「操作を代わりにやってもらえた」感覚を得られ、顧客満足度(CSAT)が大幅に向上します。
ビフォー・アフターの具体例
例えばECサイトを運営している企業の場合を考えてみましょう。
導入前(Before)
「カートに商品が入らない」という問い合わせがあった際、顧客からメールで状況説明を受け取り、サポート担当者がスクリーンショットを依頼し、何度もやり取りをして解決。解決までに平均30分以上かかっていました。
導入後(After)
ビデオ通話によるカスタマーサポートのリンクを導入した後は、顧客が「ビデオ通話ボタン」を押すだけで担当者とつながり、画面を一緒に確認しながら数分で解決。結果として、解決時間は10分以内に短縮され、顧客満足度調査でも高評価を得られるようになりました。
導入効果のまとめ
有人チャットとビデオ通話をかけあわせたカスタマーサポートツールを導入することで、企業は顧客対応において大きな変革を期待できます。有人チャットとビデオ通話や画面同期を活用することで、従来よりもはるかに短時間で課題を解決できるようになり、解決までの平均時間を大幅に短縮できます。これにより顧客は待たされるストレスから解放され、結果として顧客満足度(CSAT)が向上します。
また、効率的な対応が可能になることで、サポート担当者の業務負担も軽減されます。長時間にわたるメール対応や、繰り返しの電話説明が減少することで、スタッフは本来注力すべき高度な案件に集中できるようになります。その結果、企業全体としてのサポート品質が底上げされます。
さらに、顧客がスムーズに問題を解決できるようになれば、サポート対応の不満から離脱するケースも減少します。これは顧客離脱率の低下につながり、長期的な顧客維持とロイヤリティ強化に寄与します。加えて、購入前の不安を解消する場面でもビデオ通話によるカスタマーサポートは効果を発揮し、オンライン接客によってCVR(コンバージョン率)の改善にも直結します。
ビデオ通話の導入は単なる業務効率化にとどまりません。顧客との接点を質的に向上させ、企業の売上やブランド価値を高める戦略的な投資になります。カスタマーサポートツールは、サポート部門を従来の「コストセンター」から、企業成長を支える「顧客体験を生み出す戦略部門」へと変革する力を持っています。
カスタマーサポートツールの活用シーン
カスタマーサポートツールの導入は、業種やビジネスモデルによって効果の現れ方が異なります。特にLiveCallは「リアルタイムで顧客とつながる」という特性を持つため、多様な業界で具体的な成果を生み出すことができます。ここでは、代表的な活用シーンを紹介します。
ECサイト:購入前の不安を解消してコンバージョン率を改善
ECサイトでは、商品を「実際に手に取って確認できない」という特性上、顧客は不安を抱えやすい傾向があります。「サイズ感が合うか心配」「操作が難しくないか」「保証はどうなっているのか」などの疑問が残ったままでは、購入をためらい、カートに商品を入れても離脱してしまうケースが少なくありません。
ここでLiveCallを導入すると、顧客はWebサイト上のボタンをクリックするだけで、サポート担当者とビデオ通話が可能になります。担当者はカメラ越しに商品の実物を見せながら説明したり、画面共有で保証内容を案内したりできます。これにより顧客は安心感を得て、購入に踏み切りやすくなり、CVR(コンバージョン率)が向上します。
金融機関:非対面相談で信頼性を強化
金融商品や保険は内容が複雑で、顧客は「しっかり説明を聞いてから契約したい」と考えることが多い分野です。しかし、従来の電話やメールでは十分な説明が難しく、顧客は不安を抱えたまま判断を迫られることがありました。
LiveCallを利用すれば、担当者がビデオ通話を通じて資料を画面共有しながら説明できます。顧客は担当者の表情を見ながら安心して相談でき、疑問があればその場で解決可能です。これにより、非対面でありながら対面相談に近い体験を実現でき、顧客からの信頼性を強化できます。
医療・ヘルスケア:オンライン診療やサポートで利便性を向上
医療やヘルスケアの分野でも、LiveCallは大きな役割を果たします。たとえばオンライン診療や服薬指導の場面では、ビデオ通話で医師や薬剤師と直接つながり、症状や服薬状況を確認してもらえます。高齢者や育児中の親にとって、移動せずに相談できるメリットは非常に大きいものです。
また、介護や子育て用品を提供する企業でも、LiveCallを使って「正しい使用方法の説明」や「トラブル時のサポート」をリアルタイムで行えます。これにより、利便性と安心感を同時に提供でき、顧客満足度の向上に直結します。
メーカー・工務店:製品サポートや修理対応を効率化
機械や設備、住宅などの分野では、「操作が分からない」「部品が壊れた」といった問い合わせが多発します。従来は顧客に写真を送ってもらい、担当者がメールや電話で説明するしかありませんでした。しかし、これでは伝わりにくく、解決までに時間がかかります。
LiveCallを導入すれば、顧客がスマートフォンのカメラを通じて現物を見せ、その場で担当者が状況を確認しながら案内できます。必要であれば、画面共有でマニュアルを一緒に確認しながら対応できます。これにより、問い合わせ対応時間を短縮し、現地訪問の回数も削減できるのです。
LiveCallは、導入する業界によってさまざまな効果を発揮します。たとえばECサイトであれば購入前の不安を取り除くことで売上拡大につながり、金融機関であれば非対面相談でも安心感を与えることで信頼性を高めることができます。医療やヘルスケアの分野では、オンライン診療や服薬指導などを通じて利便性を大きく向上させられますし、メーカーや工務店では製品サポートや修理対応の効率化によって業務全体を最適化できます。
このように、LiveCallの最大の強みは、業界を問わず顧客の不安をリアルタイムで解消できる点にあります。単なる問い合わせ対応のコスト削減にとどまらず、顧客に新しい価値を提供し、サポート部門を企業の成長を支える戦略的な機能へと進化させるツールだといえるでしょう。
LiveCallと他ツールの違い
カスタマーサポートツールと一口に言っても、その機能や強みはツールごとに異なります。市場にはZendeskやFreshdesk、Salesforce Service Cloudといった問い合わせ管理に強みを持つ海外製ツールや、ChatPlusのようなチャットボット特化型の国内サービスなど、幅広い選択肢が存在します。では、その中でLiveCallはどのような位置づけにあるのでしょうか。
従来型ツールの強みと限界
問い合わせ管理ツールの代表格であるZendeskやFreshdeskは、複数チャネルからの問い合わせをチケット化して管理できる点に優れています。誰がどの案件を対応しているかを可視化できるため、対応漏れや二重対応を防ぎ、サポート体制を効率化することが可能です。
一方で、これらのツールは「問い合わせを効率的に処理する」ことに重点を置いているため、顧客が抱える問題をリアルタイムに体験的に解決する仕組みには限界があります。メールやチャットでは、顧客が状況を言葉で説明する必要があり、伝わらないもどかしさが残ってしまうのです。
チャットボット型ツールの強みと限界
ChatPlusやKARTEなどに代表されるチャットボット・AI対応型のツールは、顧客が自分で解決できる仕組みを整える点で効果的です。一次対応の自動化により、人的リソースを節約し、サポート部門の負荷を軽減できます。
しかし、顧客の問い合わせが複雑になると、チャットボットでは十分に対応できず、結局人間のオペレーターに引き継ぐ必要が出てきます。とくに「操作ができない」「現物を見て説明してほしい」といったケースでは、テキストベースの対応だけでは解決が難しいのです。
LiveCallの立ち位置と独自性
これに対して、LiveCallの最大の特徴は「リアルタイムのビデオ接客」を中核に据えていることです。問い合わせ管理やFAQのような「効率化」の枠を超えて、顧客とサポート担当者が同じ画面や現物を見ながら解決に取り組める点が大きな違いです。
たとえば、
ZendeskやFreshdeskが「問い合わせを整理して効率的に処理する」ことに強みを持つのに対し、LiveCallは「顧客の困りごとをその場で一緒に解決する」ことに強みを持ちます。
ChatPlusのようなチャットボットが「自己解決の促進」を重視するのに対し、LiveCallは「顧客に寄り添った体験的なサポート」を重視します。
つまりLiveCallは、問い合わせ管理や自動化を補完する「体験型サポートツール」として位置づけられます。企業は既存の問い合わせ管理システムやチャットボットと組み合わせてLiveCallを導入することで、顧客体験と効率化の両立を実現できるのです。
まとめ
市場には多くのカスタマーサポートツールがありますが、その多くは「効率化」や「自動化」に焦点を当てています。一方でLiveCallは、「顧客の不安をその場で取り除くリアルタイム支援」を強みに、サポート部門を顧客体験の最前線へと押し上げます。この差別化ポイントこそが、LiveCallが他ツールとは一線を画す理由です。
導入企業の声・成果イメージ
LiveCallを導入した企業からは、顧客対応の質や業務効率において大きな改善が見られたという声が数多く寄せられています。ここでは、その一部を具体的な成果イメージとともに紹介します。
あるECサイトを運営する企業では、導入前は購入直前の問い合わせに対応するのに平均30分以上かかっていました。顧客がエラーメッセージを説明するのに手間取り、メールのやり取りが何度も往復していたからです。しかし、LiveCallを導入した後は、顧客がその場で画面を共有できるようになり、対応時間は平均10分以下に短縮されました。その結果、問い合わせをした顧客の多くがそのまま購入に進み、成約率が20%以上向上するという効果が確認されています。
また、金融機関のオンライン相談窓口では、LiveCallによるビデオ通話が「安心感につながった」と評価されています。従来の電話相談では契約内容の説明が不十分だと感じていた顧客が、資料を画面共有しながら説明を受けられるようになったことで理解が深まり、契約率が顕著に改善しました。担当者からも「顧客との信頼関係が築きやすくなった」という声が上がっています。
さらに、医療・ヘルスケア分野でもLiveCallは活用されています。ある薬局チェーンでは、服薬指導をビデオ通話で行えるようにしたことで、高齢者や子育て世代の来店負担が減少しました。利用者アンケートでは「わざわざ店舗に行かなくても顔を見ながら相談できて安心」という声が多く寄せられ、リピート利用率の上昇につながっています。
製造業や工務店の現場でも、LiveCallを活用したサポート体制の強化が進んでいます。従来は現場にスタッフを派遣して対応していた修理やメンテナンスの依頼が、LiveCallを通じて遠隔で解決できるようになり、訪問件数を大幅に削減。その結果、サポートコストの抑制と顧客対応のスピード化を同時に実現しました。
こうした事例が示しているのは、LiveCallの導入効果が単なる「便利さの向上」ではなく、売上拡大、信頼性の強化、コスト削減、顧客満足度の向上といったビジネス成果に直結しているということです。LiveCallはサポート部門を強化するだけでなく、企業全体の成長を支える戦略的なツールとして活用されているのです。
まとめ
現代のビジネスにおいて、カスタマーサポートツールはもはや「あると便利な仕組み」ではなく、顧客体験(CX)と業務効率を両立させるための必須インフラとなっています。電話やメールだけでは顧客の期待に応えきれない今、複数チャネルを統合し、迅速かつ的確に対応できる環境を整えることが、企業の競争力を左右します。
その中で、LiveCallが提供する「ビデオ通話・画面共有によるリアルタイムサポート」は、従来のツールにはない強みを持っています。顧客の困りごとをその場で共有し、一緒に解決することで、単なる効率化を超えた「安心感」や「信頼」を提供できるのです。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、成約率の改善やサポートコストの削減といった実際のビジネス成果へとつながります。
LiveCallを導入することは、サポート部門を「コストセンター」から「企業成長を牽引する戦略部門」へと進化させる取り組みだと言えるでしょう。顧客対応を単なる業務としてとらえるのではなく、新しい価値を生み出す顧客体験の場として再定義する。その第一歩を、LiveCallが力強く後押ししてくれるはずです。

サイトにリンクを貼るだけで簡単導入!
興味をもたれた方は、お気軽にお問合せください。
担当者があなたのサービスに最適な機能を提案いたします。
関連記事一覧




